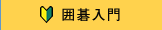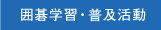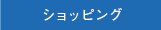ここでは週刊碁連載中の「つるりん式観る碁のすすめ~四字熟語編」で書ききれなかったこぼれ話を紹介します。(つる=鶴山淳志八段、りん=林漢傑八段)
今回も読者の方からリクエストをいただいた四字熟語を取り上げています。「彫心鏤骨」(ちょうしんるこつ)は「心に彫りつけ骨に刻み込む」こと。そこから非常に苦心して詩文などを作り上げることを意味します。「一局をものすごく苦しみながら作りあげている人は誰か」。つる&りんは趙治勲名誉名人しかいないという結論に達しました。

趙名誉名人はつるの恩師。つるは弟子として師匠の「勝負に対する厳しさ」をひしひしと感じてきたと言います。そこで本コラムではつるに内弟子時代を語ってもらいました。
- ―― 内弟子時代はどのような生活だったのですか?
- つる)弟子たちは先生のご自宅から少し離れたところにある道場に住んでいました。多い時は7人くらいいたかな。食事はおじいちゃんとおばあちゃん(先生の奥様のご両親)が用意してくださって、寮生活みたいな感じでした。
- ―― 内弟子生活ならではの日課はありましたか?
- つる)朝にマラソンをするというのが日課でしたね。ある時、みんなで寝坊して外に出てみたら先生が座って待っていたことがありました。あれは本当に怖かったです。先生は起こしにきたりしないんですよ。黙って待っているんです。それが怖い。
- ―― 趙名誉名人は怖い先生だったんですね。
- つる)怖かったですね。でも、大声で怒ったり、口うるさかったり、そういう怖さじゃないんです。例えば、よく考えないで変な手を打ったりするじゃないですか、そうすると、ため息をついて「もういいよ」って言われちゃうんです。それが一番こたえました。
- ―― 勉強をサボったりできないですね。
- つる)・・・いや、サボっていましたよ(笑)。先生がいない時はみんな道場で漫画を読んだりしていました(笑)。先生が来る時はだいたいスリッパの音でわかるんです。「パタッパタッ」って音がしたら、みんなでサッと片づけて勉強していたふりをしました。でも、たまにわざと先生っぽい足音を立ててみんなをビビらせるヤツとかがいるんですよね。そうすると「オイッ、やめろよー」とか言ってじゃれ合っていました(笑)。
- ―― 楽しそうですね。
- つる)楽しかったですよ。それに、先生も囲碁には厳しくて怖かったけど、囲碁が関係ない時にはとっても優しかったんです。弟子の誰かが入段したり昇段したりするとバーベキューをしてくださったのですが、その時は特に楽しかったですね。僕はアウトドアが大好きでバーベキューもよくするのですが、今思うと師匠の影響かもしれません。
- ―― 最後に、つるさんにとって趙名誉名人はどんな師匠か、教えてください。
- つる)囲碁に対する厳しい姿勢は本当に尊敬していますし、弟子思いの優しい先生だったと思います。実際、入段してからはほとんど怒られることもなくなって、今思えば自分が責任を持ってプロにしなければいけないという気持ちで厳しくしてくださっていたんだと思うんですよね。本当にありがとうございましたとお伝えしたいです。

趙治勲名誉名人(右前から2番目)と門下生で撮った貴重な一枚。左前端が若かりし頃のつる(鶴山淳志八段)。
記・編集K