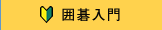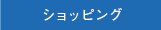朝6時半に起きて、棋譜並べをすることから1日が始まる。
朝食が終わったら、ネット碁を打ち、AIを使って研究。昼食が終わったらすぐにパソコンを開いてまた研究。夕食の時間まで碁に没頭する。
加藤千笑二段の生活は10歳の頃から基本的には同じだ。研究の内容はその時々で違っても、碁と向き合い続けていることに変わりはない。
加藤は2001年9月13日に岐阜県で生を受けた。そして生まれつき骨が弱い「骨形成不全症」という難病を抱えていた。母、裕子さんは妊婦健診で「お子さんには障がいがあります」と医師から告げられた。「覚悟してくださいね」。レクチャーを受けたあと、夫の良和さんと話して、「せっかく生まれてきたら、とにかくたくさん笑って生きてほしい」と願いを込めて「千笑」と名付けた。
骨が弱い、言葉で聞くのと実際に生活するのはまるで違う。乳児の頃は、裕子さんが授乳しようとして、自分の体にぶつけてしまっただけで骨が折れた。お風呂に入れる時は「特に緊張した」という。ほんの少しの衝撃でもこの子の骨が折れてしまう。ガラス細工のような我が子が文字通り壊れてしまわないよう、何をするにも細心の注意を払った。
児童期に入っても、骨の弱さは変わらなかった。歩行は足への負担が大きく、長くは続けられない。移動はほとんど車椅子になった。「他の子のように遊べない、自由に動けない。千笑はすごくいろいろなことを諦めて、我慢してきたと思います」と裕子さんは話す。
骨折は頻繁にあった。特に折れやすいのは足と腕。折れるたびにギプスで固定し、痛みに耐えた。「たぶん20回くらいは骨折していると思います。親から見ても本当につらそうでした」。骨を強化するための手術も経験した。
外で遊べない分、楽しみは読書とボードゲームだった。5才の頃、良和さんと図書館の本で囲碁を覚えた。最初は初心者二人で小さな碁盤で打つだけだったが、小学2年生の時、近くの公民館でやっている教室に月に1度通うようになった。
教室に通い始めて間もないある日、真夜中に右腕が折れた。救急で病院へ行ったが、固定が上手くいかず、骨が変形してしまった。「今も両腕を合わせると右腕の方が少し短いんです。千笑は右手だと碁盤の端の方に手が届かないと言っていました」。加藤は右手で打つのをやめ、左手で石を持つようになった。本人にこの事を聞くと「碁を始めてすぐの頃だったので、(打つ手を)変えるのはそんなに大変じゃなかったです」とさらりと答えた。そんなことは何でもないと思うほど、何度も骨折し、多くの我慢をしてきた。
小学4年生の時に人生の転機が訪れる。月に1度の教室と棋書によって初段の実力になっていた加藤は、少年少女囲碁大会の岐阜県代表に選抜されたのだ。
全国大会の会場には囲碁の強い子どもが全国各地から集まってくる。「千笑は自分と同じ年で六段の子がいる、ということにびっくりしたみたいです。この時を境に囲碁への取り組み方が変わりました」。
自分より強い子に会ったことは大きな衝撃だった。もっと強くなれること。強くなればプロ棋士という道があること。障がいがあっても、その道なら他の人と対等に戦えること。いろいろなことが結び付いて一本の道になった。
これだと決めた加藤の没頭ぶりは凄まじかった。「親の私からみても1日中、ずっと囲碁をしていました」と裕子さん。良和さんもそんな加藤を見て、「結果を出したら院生になれるか聞いてあげるよ」と約束した。
羽根泰正九段が主宰する泰正会に入ったのは4年生の終わり頃。プロの指導にふれ、棋力はどんどん伸びた。力試しのため、日本棋院中部総本部で行われている段級位認定大会にも機会を見つけては出場した。この頃から加藤は裕子さんが運転する車で頻繁に名古屋に行くようになる。
泰正会でも、大会でも、周りの対応は温かだった。大会では車椅子の加藤に合わせた低い机が用意され、中部総本部には多目的トイレが設置された。関わる人はみんな、できることは何でも協力してくれた。
衝撃を受けた全国大会の2年後、加藤は同じ舞台で優勝する。女子の優勝は向井千瑛六段以来、14年ぶりの快挙だった。帰りの車で加藤は「院生になりたい」と言った。結果を出したら院生になれるか聞いてあげる。父とした約束だった。優勝という快挙よりも、加藤にとっては結果を出して、院生になって、プロへの道を開くことの方がずっと大事だったのかもしれない。

第34回文部科学大臣杯・少年少女囲碁大会で優勝。トロフィーを持って記念撮影。

ご両親と。
* 後編では加藤二段の院生に入ってから現在までを描きます。