囲碁ゲームの2大要素
碁は陣地をつくるゲームだということは、お分かりいただけたと思いますが、もう一つ大事なルールがあります。
それは「相手の石を囲めば取り上げることができる」ということです。
取り上げた石は捕虜として、試合最後に相手陣地に埋めて計算することになります。
1.自分の陣地をつくる

黒は25目の地(陣地)、白は24目の地(陣地)ができました。
2.相手の石を囲んで取る
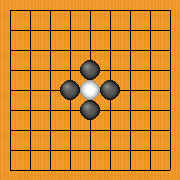

相手の石を囲めば取り上げることができます。
初めて碁を覚える方にとって、2つの要素をいっぺんに習うと頭が混乱して何が何なのか訳がわからなくなってしまうことが多々ありますから、ここでは考え方だけを理解しましょう。
この2つの要素が絡み合うために囲碁はむずかしいというイメージがでてくるのでしょうが、逆に囲碁はこれらの要素があるからこそ、面白く奥が深いゲームなんです。
ただ陣地を囲ってつくるだけでは、つまらないゲームですものね。
陣地をつくる
碁石で囲って自分の陣地をつくります。

黒石を16個使って、9目の陣地ができました。
碁盤のスミや辺を利用して陣地をつくります。

黒石9個使って、16目の陣地ができました。
碁盤のスミや辺はこれで囲ったことになります。
お互い順番に一手づつ打つゲームですから、使用する石数は極力少なく、かつ最大限の効果をあげるためにスミや辺を上手に利用します。
石は生きている
呼吸点(こきゅうてん)
右の図下の図を見てください。
赤い印■が4つありますね。これを呼吸点(呼吸ができるところ)といいます。
石の呼吸点は石の置かれた場所のナナメではなく、十字の線上にあります。

呼吸点を封じられると石は生きられない
呼吸点を全部封じられると、石は盤上で生きることはできず、取り上げられてしまいます。
つまり、呼吸点を封じるということはその石を囲んで取るということです。
自分の石を守りながら相手の石を取っちゃうぞと攻める。また攻められたら守る。そのような攻防を繰り返しながら、自分の陣地を広げていくのが囲碁ゲームの戦略なのです。
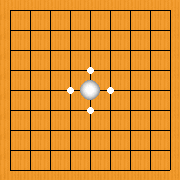
いろいろな場合の呼吸点
呼吸点は石が中央にあれば4つ、辺は3つ、スミは2つとなります。
石が複数になると、呼吸点の数もかわります。



